退職する時に必要な手続き(退職スケジュール)
投稿日:2024.03.07 最終更新日:2024.03.07
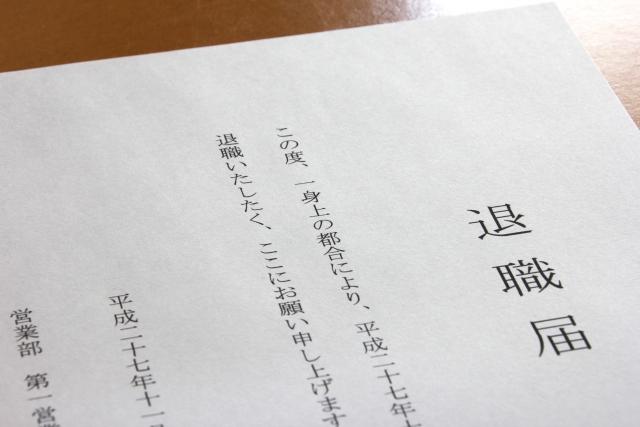
目次
退職の際にはさまざまな手続きが必要になります。
どのような手続きが必要になるのかについて、誰かが教えてくれるわけではありませんし、複雑な手続きも多々あります。また会社によって、手続きの方法が違う場合もあります。
退職に必要な手続きについては、早めに確認をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。
退職手続き
会社を退職する際には、会社に返却しなければならないものがあります。
退職日当日に慌てて手続きしたり、必要な書類を探すようなことがないように、早めに確認しておきましょう。
下記では、自己都合退職の場合の手続きの、一般的な流れについてご紹介します。
会社によって手続きが異なる場合もありますので、早めに就業規則を確認したり、担当部署に問い合わせるなどしておきましょう。
1. 会社に退職届を提出
↓
2. 業務の引継ぎを行う
↓
3. 会社に返却するもの、会社から受け取るものを確認する
↓
4. 住民税の納付方法や健康保険の任意継続制度の確認
↓
5. 退職金の確認と「退職所得の受給に関する申告書」を提出
↓
6. 退職当日
・健康保険証を返却
・健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票を受け取る
・源泉徴収票を受け取る
↓
7. 国民健康保険または任意継続または扶養家族等への切替え手続き
↓
8. 国民年金の切替え手続き
↓
9. 離職票を受け取る
↓
10. ハローワークへ行き、失業保険の手続きをする
↓
11. 退職金を受け取る
退職の意思表示
退職の意思表示をいつするかについては、多くの人が迷うところだと思います。
あまり早く辞めると言ってしまうと、職場で居心地が悪くなってしまうのでは……と気にする人もいるでしょうし、かと言ってギリギリに退職を申し出ると、職場に迷惑がかかってしまいます。
労働基準法では、「労働者が退職する際には○日前までに会社に通知しなければならない」という規定は存在しません。
民法627条1項では、退職の14日前までに意思表示をすればよいと規定されていて、解約の申し入れから14日が経過すれば雇用が終了すると規定されています。
さらに同条2項では、月給制においては月の前半に退職を申し出た場合には当月末に、月の後半に退職を申し出た場合には、翌月末に退職が成立するとしています。
しかしこの民法の規定に従って「2週間後に退職します」とすると、会社はそれまでに後任を見つけなければなりませんし、業務がスムーズに引き継がれないケースも想定されます。
そこで通常は、会社の就業規則で、業務に支障が出ないように、退職届をいつまでに提出するかについて「退職する際には○日前または○か月前までに、会社にその旨の意思表示をしなければならない」と規定されています。
ですから、退職の意思表示をする際には、必ず会社の就業規則を確認するようにしましょう。
退職願と退職届
会社によっては、退職願と退職届を同じものとして扱っているケースがほとんどですが、厳密に言うと退職届と退職願は違います。
「退職届」とは「退職を届け出る書類」で、従業員側から一方的に労働契約を解約する旨の告知書類であり、「本人の意思として退職を決定したので、届出します」という意味合いの書類です。つまり退職届の場合には、提出して受理されればその時点で退職が決定します。
これに対して「退職願」とは、労働契約の解約を願い出るものです。退職願を提出し会社に承諾された時点で、はじめて退職の効力が成立する書類なので、提出した段階では退職が確定するわけではありません。
ただし、退職願にするか退職届にするかについて、法律で特別に規定されているわけではありません。会社に明確に辞める決意を示したいのであれば、退職届の方がよいと言えるでしょう。
なお、同じような意味で「辞表」という言葉もありますが、辞表は、役員を辞任する際や公務員の退職時に使う言葉ですので、ご注意ください。
退職時に会社に返却するもの
退職時に会社に返却する主なものは、以下のとおりです。
各会社で他にも返却が必要なものがある場合もありますので、必ず総務部に確認するようにしましょう。
・健康保険被保険者証(本人と家族のものすべて)
・社員証
・社章
・名札や名刺
・机やロッカーの鍵
・制服やパソコンなど会社から貸与されていたもの
・就業規則や、社内のマニュアル
健康保険被保険者証は、退職日までしか使えません。
本人の健康保険被保険者証はもちろん、家族の分も忘れずに返却してください。
まれに退職日以降もその健康保険被保険者証を使ってしまう人がいますが、後で医療費の請求が届くなど手続きが面倒になるので、退職日当日に忘れずに返却するようにしましょう。
会社から受け取るもの
退職時に会社から受け取るものは、以下のとおりです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証(会社が管理している場合)
・年金手帳(会社が管理している場合)
・源泉徴収票
・退職証明書(必要な人だけ)
・厚生年金基金加入員証
・退職金や未払い賃金
雇用保険被保険者離職票は、失業保険を受給するために必ず必要となる書類です。
退職して2週間以内に発行されるのが一般的ですが、会社によっては本人が請求しないと発行してくれない場合もあるので、もし2週間過ぎても発行されない場合には問い合わせてみましょう。離職票の受け取りが遅れると、失業保険の支給も遅れてしまいます。
雇用保険被保険者離職票は、在職期間が短くて失業保険をもらうことができない場合や、転職先が既に決まっていて失業保険をもらう予定がない場合でも、必ずもらっておきましょう。前後の会社を通算して失業保険をもらえる場合もあるからです。
失業保険は、正式名称は「求職者給付の基本手当」ですが、ここでは分かりやすく「失業保険」と記載しています。
健康保険の任意継続制度の利用
健康保険の任意継続制度の利用は、国民健康保険に加入する場合とどちらが有利か、退職前にぜひ調べておきましょう。
配偶者がいて、配偶者が会社に勤務している場合には、その扶養家族として加入できる場合もあるので、配偶者の勤務先に、扶養家族として申請することができるかも確認しておきましょう。
未払い賃金
未払い賃金がある場合には、返還期限が法律で決められています。
労働基準法では、「使用者(会社)は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった際に、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称のいかんを問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と規定していて、これらの賃金または金品に争いがある場合には、使用者は、異議のない部分については、7日以内に支払い、または返還しなければならないとしています。
退職が決定しているにも関わらず、労働者を引き留めるために、未払いの賃金や積立金が支払われないというトラブルがあることから、労働基準法では会社に対して金品の返還を義務付けて、退職者の生活を守ろうとしているのです。
使用者(会社)が賃金を支払わない場合には、仮処分、労働審判などの裁判所の手続きを利用する方法がありますが、コストと費用がかかりますので、まずは労働基準監督署に相談に行かれることをおすすめします。
退職金
退職金は、誰にでも支給されるわけではありません。
労働基準法でも、退職者には退職金を支払わなければならないという規定はありません。
会社に退職金制度がある場合には、退職金規定で退職金額と支給日を確認して「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。
なかには、退職金規定に定められた金額より少ない退職金しか支給されない会社や、退職金規定で決まっているにも関わらず、退職金を全く支給しない会社もあります。
「退職金規定なんて見たことがない」という人が大半だと思いますが、事前にしっかりと規定を確認しておくことが重要です。



